ここでは、ロストワンの特徴を解説します。また、1分でできるタイプ診断や、克服方法も紹介するので参考にどうぞ。アダルトチルドレンの「ロストワン」について、詳しく知りたい方はぜひ覧ください。
関連記事:【無料】アダルトチルドレンタイプ診断|性格と特徴も解説
ロストワンとは

ロストワンとは、アダルトチルドレンの7タイプのうちのひとつです。
中でも、集団の中での存在感が薄く、忘れられがちな人のことを指します。自分を表現することが苦手で、周りからは「何を考えているかわからない人」と思われることが多いです。
日本語に訳すと「自分を失っている人」や「忘れられた子」という意味になります。
『ロストワン』
一般社団法人リアルトレジャー
役割:いない子・迷子・隠れる子
物陰にじっと潜むロストワンは、家族の目から消えている【忘れられた手のかからない子】
「ロストチャイルド」や「いない子」と呼ばれることもあります。
ロストワンタイプチェック診断
まずは、自分がロストワンなのかチェックしてみてください。4つ以上あてはまると、ロストワンの可能性が高いです。
関連記事:【無料】生きづらさ診断|3分で簡単にできるセルフチェックテスト
ロストワン性格の特徴

ロストワンは、実はアダルトチルドレン(AC)の中でも特異的な存在です。
というのも、ほかのタイプではそれぞれ特徴があったと思うのですが
ロストワンは「特徴がないことが特徴」です。
そのため、ほかのアダルトチルドレン(AC)タイプより気づくのが、遅れます。
しかし分かりづらいものの、次の7つの特徴があります。
特徴①周りからは何を考えているのか分からない
まず1つ目の特徴として、何を考えてるか分からないというのがあげられます。
どういうことかというと、他人から見た際に、大人しすぎて無口であったり、何かの拍子に急に問題を起こしてしまうけど、理由が分からない。これらのことから「何を考えているかわからない人」という特徴があります。
職場や学校の中だけではなく、家庭の中でも「○○くんいたの?」「○○ちゃんいたの?」みたいな存在感のない人として見られることが多いです。
特徴②「私なんてどうせ……」という価値観を持っている
2つ目の特徴として「私はいつも一人ぼっちだ」とか「私がいなくてもどうせこの世界は変わらない」あるいは「私なんてどうでもいいんでしょう」とか「自分が構ってもらえないんだ」という価値観を持っています。
そのため、常にどこか悲観的なオーラを持ってしまっていることもあります。
特徴③感情を自分の中に留めて自分を表現しようとする
この特徴③がもっともロストワンに根付いている特徴です。
どういう事かというと、例えば他のACタイプであるヒーローとかスケープゴートは、それぞれの価値観からくる感情をベースに行動することで特徴を出しますが、ロストワンは感情を自分の中だけにとどめ「行動しない」ということで特徴を出します。
例1:ヒーロー
「頑張らなければ認められない」という価値観から、がむしゃらに頑張るという行動で感情を表現する。
例2:スケープゴート
「どうせ私が悪い」という価値観から、問題行動でを起こすという行動で感情を表現する。
例:ロストワン
「どうせ私なんかいてもいなくても変わらない」という価値観から、行動せず感情を心にとどめ、存在感を消す。
だから他のアダルトチルドレンの特徴と比べて特徴が分かる辛いというのが特徴なのです。
特徴④心の中が孤独感でいっぱい
そういう価値観を表に出すのではなくて「自分の中で全て消化しようとする」のがロストワンなんです。けどロストワンの心の中は孤独感がいっぱいなんです。
なんでかと言うと「ずっと自分のことを誰も構ってくれなかった」「自分は何を言っても意見が通らない」。そんな経験が過去にあるので「自分は誰にも構ってもらえない人間なんだ」という風に思ってしまって孤独感がいっぱいなんです。
そのために他人から何か言われたとしても「○○ちゃんすごいよ」とか言われてたとしても「どうせ嘘だろう」とか、そういう風に思ってしまう。
特徴⑤自分の存在価値を見出すことができない
孤独感で満たされているロストワン。
そのため自分の存在価値すら自分で認めることができないというのも特徴の1つです。実はこの問題ってすごくすごく深くて、他のアダルトチルドレンのタイプは何かを表現することによって自分の存在を認識しようとするんです。
けどロストワンというのはそもそも感情を表現できないため、自分の存在すらも認めることができない。だからすごく孤独で存在なんです。だからロストワンはACタイプの中で一番わかりづらくて一番しんどいタイプなんです。
特徴⑥自分の意見を言うのが苦手
ここからはロストワンの苦手な事から特徴をお伝えしていきます。
全部で2つあって、1つ目の苦手は「自分の意見を言うこと」です。これはなんでかと言うと過去に自分の意見を言った時に「そんなのどうでもいい」とか言われたり、態度で示されたり、あるいは発言すらも無視されたという経験があるんです。
そのため、何かを言ったところで何も起こらないし、意見を言ったところで否定されると思ってるから、自分の意見を言う事ってのがすごく苦手です。
特徴⑦自分で決めるのが苦手
さて、2つ目の苦手は「自分で決めること」です。
さっきの意見をするとちょっと被るのですが、意見をした時めちゃくちゃ否定されて結局相手の意見に合わせる。
例:
お母さんとご飯に行ったときに「私はパスタが食べたい」って言ったのに、お母さんが「○○ちゃん、パスタじゃなくて、ピザを食べよう」と言われ、合わせてしまう。
それがたまたまだとか、その時だけで、今後はなかったとかだったらいいのです。
けれどロストワンの家庭というのは、それを何回も何十回も繰り返されるわけです。そうすると「自分の意見を言うことはダメなんだ」とか「自分で決定してもどうせ聞いてもらえない」という風に思ってしまうんです。だから決定することが苦手なんです。
決定することで自分がまた傷つくとか、どうせ何もわかってもらえないっていう思いを強化して孤独になってしまうので、「決定する」ということをやらなくなっちゃうんです。
関連記事:生きづらい人生になる7つの原因|なぜ苦しくてしんどいのか分からない人へ
ロストワンになる原因

どんな原因でロストワンになってしまうのでしょうか?
一昔前までは、ロストワンの99%が「ネグレクト育児放棄」が原因であると考えられていたのです。しかし、最近の研究では、半分は「ネグレクトや育児放棄」かもしれないが、半分はそれ以外の要素が関連しているという可能性が高い、という風に意見が落ち着いてるところです。
それではその原因を大きく3つに分けて解説していきます。
原因①ネグレクト(育児放棄)
1つ目はネグレクトや育児放棄です。
それらの行動は「自分なんて構ってもらえない」ってのが露骨に態度で示されてるわけです。だから自分なんて存在価値がないし、自分なんていてもいなくてもいいし、自分なんて構ってもらえないんだっていう風に思ってしまうわけです。
それが一つ目の原因です。
原因②過干渉
しかしながらその逆パターンもあります。「ネグレクト=放置」ですが、「過干渉」によってもロストワンという性質が生まれてしまうということが、近年の研究では主流となっています。
これはどういうことかと言うと、過干渉は、子供に親が「こうしなさいああしなさい」とか「あれはダメ。これはダメ」とめちゃくちゃ自分の意見を押し付けます。つまり、子供が決定する権利を持っていることも、その権利を剥奪して「あなたのためだから」と親自身が決めてくる。
先ほどのパスタの例と少し似ていますね。
例:
子供はAちゃんと遊ぶのが好きだけど、お母さんが「Aちゃんの家は評判悪いから、Aちゃんと遊ぶのはやめなさい。B君と遊んだほうがいいから、そっちにしなさい」と言ってくる。
だから、自分が何かやろうとしても「いや、お母さんはこうした方がいい」とかお父さんが「こうした方がいいぞ」みたいなことを言ってきて、それを無視すると態度に出されたり、報復されたりする。
だから「自分の意見なんて何を言っても無駄だ」と思い、ロストワン化するというのが二つ目です。
原因③兄/姉がすでにACの場合
最後三つ目です。これは末っ子に多いパターンです。
兄弟がめちゃくちゃ優秀すぎて自分は何をしても勝てない。あるいは、兄や姉がそもそもACの場合に起きやすいです。
例:三人兄弟で兄→姉→弟の場合
一番上の長男がヒーロータイプの優等生でめちゃくちゃ頑張って凄い成績を収めてる。そうするとよくあるパターンとして長女とかが荒れてスケープゴートになっている。
こんな状況だと、長男は親に良い意味で注目され、長女は悪い意味で注目されます。そして両親は、長男をちやほやし、荒れてる長女のケアで手一杯になるんです。
だから、一番下の子には両親の余力がなくなって、その子はロストワンし、最終的には「○○ちゃんは手間がかからなくて、ありがたい。でもいるかいないのかわからないよね」となるわけです。
脱線話(きょうだい児):長男長女だけどロストワン化
先ほど「ロストワンは末っ子に多い」と言いましたが、長男長女でもなる場合があります。
さて、あなたは「きょうだい児」という言葉をご存じでしょうか?
障害のある子の兄弟姉妹のことを「きょうだい児」と呼びます。
きょうだい児には、「障害のある子に手がかかるため親に甘えられない」「きょうだいのことでいじめられる」など、独特の悩みがあります。
DIAMOND ONLINE
弟や妹が障がい児(発達障がいや身体障がいなど)だった場合。どうしても両親はそちらの方が大変だから障がいのある子につきっきりになってしまいます。
だからその子が生まれた時には、きょうだい児は「何とか両親の関心を引こう」とヒーローを演じたり、スケープゴートになったりします。
ところが、何をやっても両親の関心を引くことができない場合、あきらめてロストワン化することがあるんです。
ロストワンの克服方法
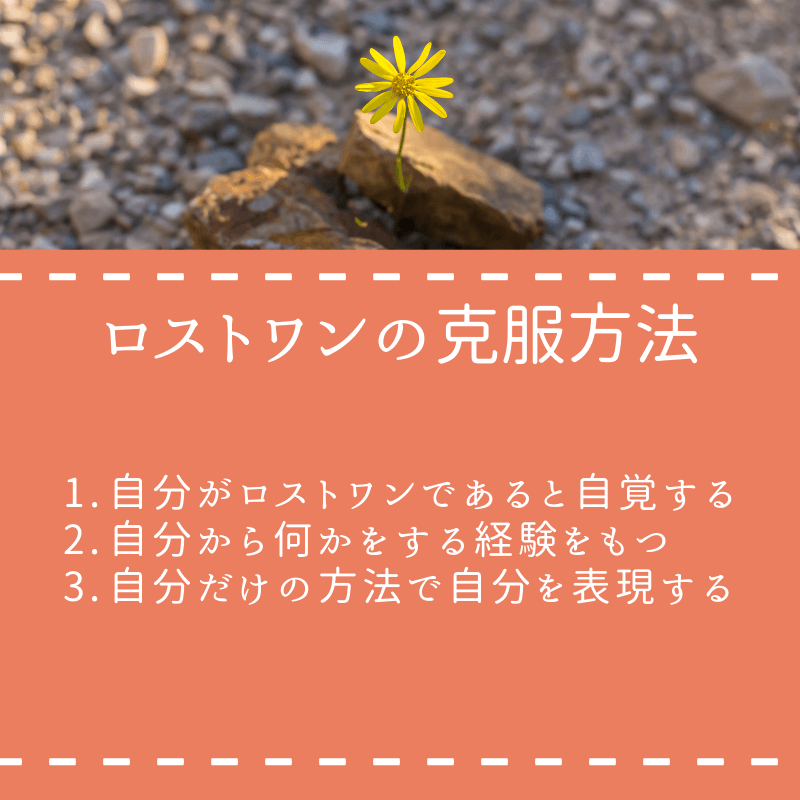
克服方法①自分がロストワンであると自覚する
「自覚すること」これが克服の一歩目です。
ロストワンの人がその役割をずっと続けてきた理由として。
例:
お母さんとお父さんが「○○ちゃん今日は何が食べたい?」って言った時に「・・・」と何も言わないんです。
だから続けて、
両親「今日ハンバーグにしようか。」
子供「・・・」
両親「う~ん、じゃあハンバーグにしようか」
子供「…うん」
みたいな話をするわけなんです。
これ、どういう事かというと、今までロストワンは「聞いても答えない事で相手が痺れを切らして助け舟を出すまで無言のまま待ってる」みたいな戦略で生きてきたんですね。
今までは無言のまま待ってて良かった。そしてそれによってさらに存在感も薄まっていた。でも本当はそれを突破しなきゃいけないわけです。
克服方法②自分から何かをする経験をもつ
じゃあ、自覚した後に何をすればいいのか?
それは「助け舟を出してくれるのを待つ」のではなくて「自分から何か行動する」という経験がいるわけです。
でも今までやってこなかったから、めちゃくちゃ勇気がいるのは事実です。だからその勇気を出すために例えば周りの人に頼ってみたりカウンセラーに頼ってみたり。
あるいは誰も知り合いのいない居酒屋とかバーにいって隣に座った人とか、マスターとかちょっと話してみるみたいな。なんでもいいので「自分から」という一歩踏み出すことが大切です。
克服方法③自分だけの方法で自分を表現する
あと、これは私がロストワンの方とかかわってきた経験からいえる事なのですが、ロストワンって芸術と相性がいいんですね。
今までロストワンを克服してきた方は「絵画であったりとか、歌や楽器、演劇といったところで自分を表現する」。そんなところに自分の感情を出すことを見出して、それによって自分の心が回復していったというパターンが多いです。
もし、あなたが芸術分野に少しでも興味があったら、やってみるのも克服の第一歩です。
ロストワンの強み
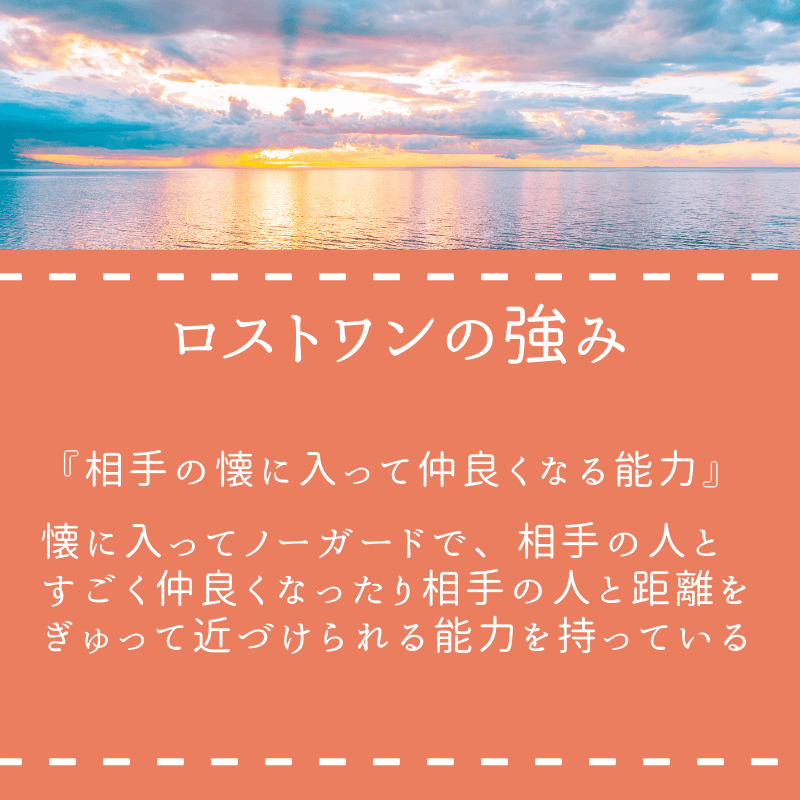
さて、ここまでたくさんの事をお伝えしてきました。
最後のひとつだけ「ロストワンの強み」を紹介していきます。
ロストワンの強みっていうのはある意味存在感を消すっていうのは、裏を返すと「どんな人のところでも、その懐にスッて入り込むことができる」のです。
相手の懐に入って仲良くなる能力
自分が意図してないにしろ、懐にスッて入り込める能力があるんです。
今はきっと懐に入っているとも気づいてないし、そこにいても何も言わないでただ空気と同じようになってるかもしれません。
しかしそれを使いこなせれば、懐に入ってノーガードで、相手の人とすごく仲良くなったり相手の人と距離をぎゅって近づけられる能力を持っているんです。
だからロストワンの中の「私なんてどうでもいいんだ」とか「私は孤独なんだ」っていうのを紐解いていくことで、ものすごく人付き合いが上手な愛される人になるのです。



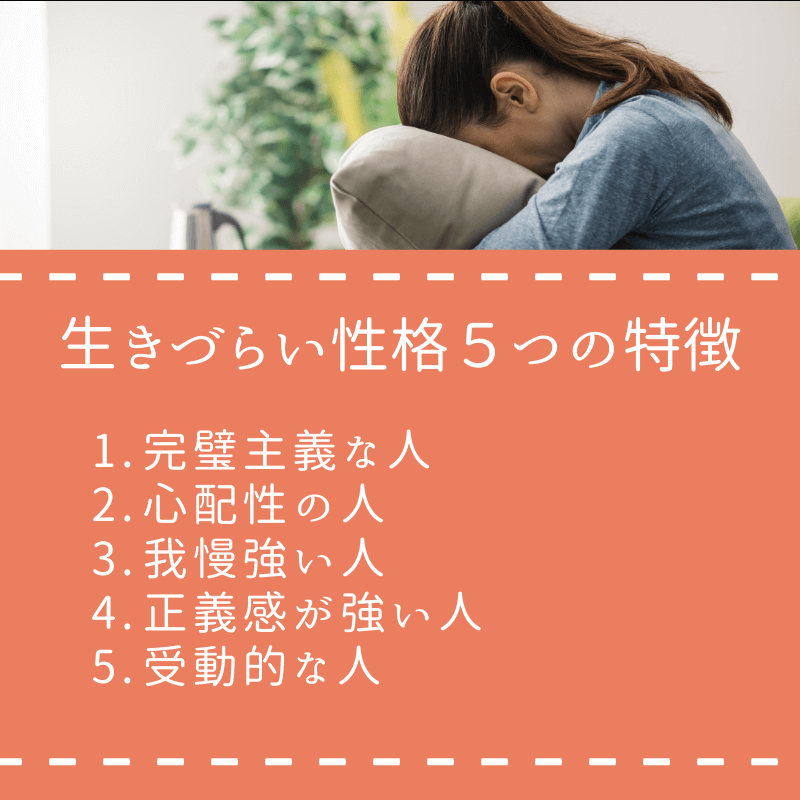

コメント
家庭内の条件が揃いに揃っているし、読めば読むほど自分でびっくりしました。
自分では当たり前だと思っていた思考が細かく解説されていて
モヤモヤが少し軽くなった気がします。
この記事を読んで「そんな自分を愛してあげよう」と客観視することができました。
ありがとうございます。